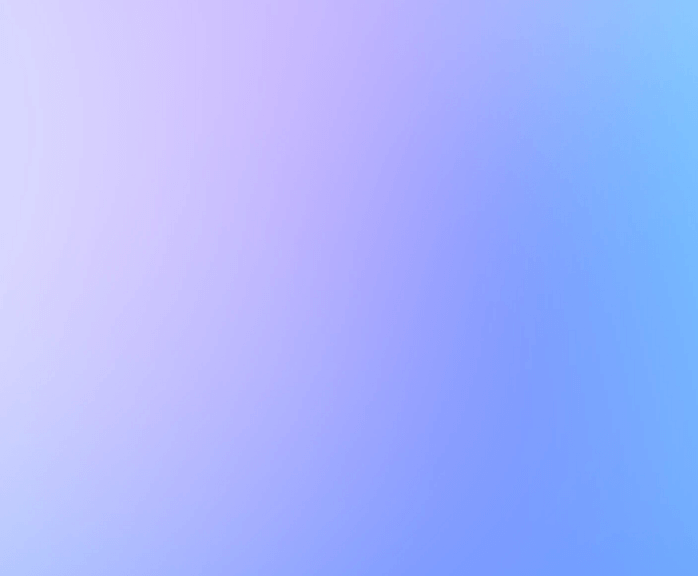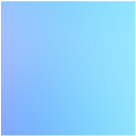フィナンシャルテクノロジーの優位性
- ・ 金融の勘定系システムの開発・運用・保守で長期的な実績
- ・ 新旧の技術を利用した多様な開発案件を手掛ける
- ・ 技術者としての誇りが成長を支える
課題
ITのチカラで、金融ビジネスの生産性を変える、
AIを使った新たな業務支援アプリケーション
ネットバンキング、オンライン決済、ATMなど人と銀行の接点のほとんどをITが担う時代になっている。このような“当たり前”を支えるのが金融ネットワークインフラだ。フィナンシャルテクノロジーは、多数の地方銀行が乗り入れる地銀共同センターの開発・運用を長い間、担っている。そこで稼働する勘定系システム「BeSTA」は金融機関とお客様をつなぐネットワークの中継点となる重要な社会インフラだ。
「地銀共同センターの開発環境は、記録メディアなどの持ち込みを金属探知機でチェックするので、私たちはベルトやアクセサリーなども外して入室します。これだけセキュリティが厳格なのは、非常に重要な社会インフラだからで、それを支えているという誇りが私たちのやりがいになっています。」
S.Fは、入社以来、BeSTAを専門としてきた有識者で、勘定系融資チームの開発リーダーだ。2019年1月のある日、AIを使った新たな業務支援アプリケーションの開発プロジェクトにアサインされた。
「人工知能を利用し、経験のないOSでシステムを作ると聞いて、最初は緊張しました。PJは実際、これまで私が扱ってきたCOBOL言語によるメインフレーム開発とはまったく異なるものになりました」
取り組み
OSはLinux系、言語はPythonで、
クラウドに仮想サーバを置く、未知の開発PJに挑戦
PJの目的はAIによる類似文書検索技術を利用して、銀行の稟議書作成を支援するアプリケーションの開発だ。稟議書とは金融機関が融資判断のために作成する重要な文書で、業績や資金使途、返済能力の判断根拠等が書かれている。作成する際は過去の類似した稟議書の記載を参考にするが、膨大な量の稟議書の中から参考になる類似案件を探し出すのは困難な作業になる。また行員の経験や技量によっては、かなり時間がかかり、しかも、記載内容にバラつきが発生するといった課題もあった。
「今回の開発は、OSはLinux系、言語もPython等とまったく経験のないもので、しかも、クラウド上に仮想サーバを置くという今までに経験のない技術を駆使したものでした」
サーバの仮想化は設置台数や場所が大幅に削減できるだけでなく、初期構築の手間が格段に減るため、近年はさまざまな業界で導入が進んでいる。しかし、SEに専門知識がないと構築も運用も難しい。S.Fは、スタートからさまざまな技術や知識の習得に追われた。
結果
開発とはいつも、これまでにない新しいものを作ること。
SEの仕事に挑戦は欠かせない。
S.Fが携わったAI検索システムは、業界や企業規模、融資額、案件の特徴などのフリーワードを入れると、AIが参考になる過去の稟議書をサジェストしてくれ、経験が浅い行員でも、良い稟議書の書き方を習得するためにも役立つ。
「長く融資に関するシステム開発を担当してきたので、そこの知識はあったのですが、技術面では新たに学ぶことが膨大にあって大変でした。開発とはいつも新しいものを作ることなので、常に挑戦はつきものですが、今回は技術面でかなり飛躍できたと思います。銀行様への開放予定日を延期することなくリリースができた時は本当に嬉しかったです。自分自身、このPJで成長することができ、新しいことをまだまだ吸収できるという自信にもなりました」
S.Fらの奮闘の結果、AIによる類似文書検索アプリは、無事、リリースに至り、金融機関に導入された。今後は、作成した稟議書の記載をAIがチェックし、適切な文言をサジェストする機能の開発も目指しているという。近い将来、融資担当の行員が最も苦労する業務においてAIの支援により大幅に効率化される日が来るかもしれない。
「地銀共同センターには他のシステムベンダーも参画していますが、こと融資に関する案件はフィナンシャルテクノロジーが受注しています。その信頼をもっと大きなものにするために、今後は新しい技術やプロジェクトマネジメント力をもっと高めていきたいと思っています」